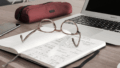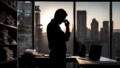~行政書士にとって「目的設計」が成功の9割を決める理由~
「そろそろホームページを作らなきゃ」行政書士として開業した方が、そう思うタイミングは人それぞれです。名刺にURLを載せるため、SNSでリンクを貼るため、なんとなく必要そうだから。そんな理由でとりあえず作る方がとても多いのが現実。
しかし、“とりあえず”で作ったホームページほど、集客や信頼形成に失敗しやすいことをご存じですか?
なぜなら、ホームページとは単なる“看板”ではなく、「営業・広報・信頼構築・教育」のすべてを担う、事務所の戦略そのものだからです。
なぜホームページに「目的」が必要なのか?

ホームページはネット上の「顔」であり、時にはあなたよりも多くの時間を顧客と接する存在です。そのホームページに目的がなければ、見に来た人にとっても価値を感じられないものになります。
たとえば――
こういった「不安」や「疑問」に対する答えが書かれていないサイトは、すぐに閉じられてしまいます。つまり、目的を持たないサイトは“集客どころか、信頼を失う”結果になる可能性があるのです。
ホームページの目的は「1つ」に絞るべき?
よくある勘違いが「いろんなことができるホームページが良い」という考えです。
実際には、多機能なサイトよりも、「何のためのサイトなのかが明確なもの」の方が圧倒的に強いです。
行政書士のホームページの目的は、主に以下の4つのどれかに当てはまります。
ここで重要なのは、「全部やろうとしないこと」。最初の段階では、1〜2の目的に絞って設計し、役割を明確にした方が成果が出やすくなります。
私は集客型に特化して、まずはSEO対策を施したコラム記事の量産をし、ある程度できた段階でブランディング型に力を入れております。
目的が曖昧なサイトがやりがちな失敗例
目的のないサイトは、何が悪いのか。よくある失敗例を挙げます。
①メニューが散漫
「業務案内」「プロフィール」「ブログ」「アクセス」…一見まとまっていそうでも、優先順位がなく、ユーザーが迷う構成になっていませんか?
②誰に向けたサイトなのかが不明
相続専門なのか、建設業許可に強いのか、それとも外国人対応なのか…。ターゲットが定まらないと、読み手に「自分には関係ない」と思われてしまいます。
③「更新されてない=やってない事務所」と誤解される
目的意識なくブログを始めた結果、半年以上更新がない状態に。これはかえってマイナスイメージを与える典型例です。
ホームページの目的を明確にするための3つの質問
ホームページの設計を始める前に、この3つの質問を思い描いてください。
これらの問いに明確に答えられれば、あなたのホームページは単なる「名刺」から、強力な「営業装置」へと進化していきます。
成功している行政書士は「目的から逆算している」
集客に成功している行政書士の多くは、ホームページを営業戦略の一部として設計しています。
これらは、全て「目的が明確」で「設計に基づいた運用」をしているからこそ生まれた成果です。
目的なきホームページは、むしろ機会損失

ホームページ制作は、行政書士として独立・開業したときの最初の“投資”の1つかもしれません。しかし、「とりあえず作る」「他の人もやってるから」では、ただの“デジタル名刺”で終わってしまい、本来得られるはずだった集客や信頼獲得のチャンスを、自ら捨てていることになりかねません。
むしろ、目的のないホームページを置いておくことは、存在しないよりも悪影響が出るケースすらあるのです。たとえば、「更新がない」「誰に向けた内容か分からない」「問い合わせしづらい」そんな印象を持たれてしまえば、あなたが本来持っている実力や誠実さも伝わりません。
ホームページは、あなたの代わりに24時間働く営業担当であり、見込み客との最初の接点です。だからこそ、「誰に何を伝え、どんな行動を促したいのか」という“目的”を明確に持つことが最も重要です。
そしてこの目的は、単に「問い合わせが欲しい」といった表面的なものではなく、
こうした「戦略的な視点」で決めていく必要があります。
目的がはっきりすれば、必要なページ構成も、書くべき文章も、配置する画像や導線も変わってきます。つまり、「設計図がある家づくり」と同じで、全体のクオリティが根本から違ってくるのです。
行政書士専門のWebサポートを行っている当方では、開業準備中からの設計相談も受け付けています。
「どこから手をつければいいかわからない」
「サイト設計を一緒に考えてほしい」
そんな方は、ぜひお気軽にご相談ください。目的が明確になるだけで、ホームページは成果を出すツールへと変わります。