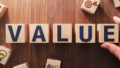多くの行政書士がホームページを「名刺代わり」に作っています。事務所の基本情報を載せて、簡単な業務案内とプロフィール。これで十分だと思っていませんか?
しかし、今やその考え方では選ばれません。名刺代わりのホームページという時代は終わったのです。
ホームページは、24時間働く営業マンに変身させることができるツールです。ただ情報を載せるだけでなく、「検索ユーザーに響く構成」や「問い合わせまでの導線」を意識するだけで、反応率は劇的に変わります。
このページでは、「ただの名刺代わり」で終わらせないホームページの設計と、集客できる考え方について解説します。
ホームページの役割を“営業ツール”として捉える

名刺代わり=存在証明。しかし、行政書士の仕事は「相談を受けて信頼を得て、依頼を獲得する」ことです。ホームページはその第一接点として非常に重要です。
営業ツールとしての役割には―
つまり、読むだけで納得できる営業トークが必要なのです。
誰に向けて・何を伝えるかを明確にする
名刺代わりのサイトは、読み手を意識せず、「自分の紹介」をするだけで終わりがちです。集客できるホームページにするためには、ユーザー視点に立ったコンテンツ設計が欠かせません。
たとえば―
このように、「誰がどんな悩みをもって検索しているか」を想定し、「あなたに関係のある内容です」と伝えることで反応率が上がります。
コンテンツの力で「信頼」を築く

行政書士の業務は「見えにくい」「比べにくい」と言われます。だからこそ、信頼性を文字や写真でどう伝えるかが勝負です。
検索者は、「この人に相談しても大丈夫か?」を常に考えています。そこをコンテンツでクリアすることが、問い合わせへの一歩につながります。
「導線設計」がなければ、問い合わせにはつながらない

いくら良い文章・見た目でも、「どこから相談すればいいのか分からない」ページでは、読者はページを離れてしまいます。反応を得るために必要なのは適切な導線設計です。
ホームページ全体が、「迷わず相談できる流れ」になっていることが鍵です。
まとめ:「ただ作る」から「戦略的に育てる」へ
行政書士のホームページは、単なる「事務所の紹介」や「連絡先の掲載」だけで終わってしまうケースが多く見られます。しかし、それではせっかくの訪問者を何も伝えられないまま、ただ通り過ぎさせてしまうことになります。
名刺のような情報提供で満足していたら、本来獲得できるはずだった見込み客との接点をみすみす失うことになるのです。一方で、「誰に・何を・どう伝えるか」という視点で設計されたホームページは、あなたの代わりに毎日・24時間働く“営業パートナー”になります。
「相談したい」「問い合わせてみたい」という心理が生まれます。
ホームページは“完成”がゴールではありません。むしろ公開後からが本番です。
記事を追加し、設計を見直し、アクセス状況を分析して改善する──そうやって少しずつ育てていくことで、資産として機能するホームページに成長していきます。
「ホームページは名刺代わり」では、もったいない。
これからの時代、行政書士の信頼や実績は“検索結果”や“サイトの内容”で評価されるようになります。
ぜひ今一度、「誰に、何を伝えるために、どんなホームページを持つのか?」を見直してみてください。