「ホームページって、とりあえず作ればいいんでしょ?」
そう思って適当に作ったサイト、実は“ほとんど見られていない”かもしれません。
行政書士の業務は、一般の方にとっては馴染みがなく、「何をしてくれる人なのか」が伝わらなければ、どんなに資格があっても選ばれません。そして、いまや相談者の多くは、まずGoogleで検索して“信頼できそうな行政書士”を探す時代です。
つまり、ホームページは「名刺代わり」ではなく、営業マンであり、受付窓口であり、信頼を得るための最大の武器なのです。
ところが…
こういった「設計ミス」があると、どんなに頑張って書いた文章も読まれず、チャンスを逃してしまいます。
この記事では、WEB集客に成功してきた行政書士の視点から、初心者でも今日から実践できる「成果につながる設計のコツ」を7つに絞って解説します。
これから開業する方も、今あるサイトを見直したい方も、ぜひチェックしてみてください。
【ターゲットを明確に】「誰に何を提供するか」を絞り込む
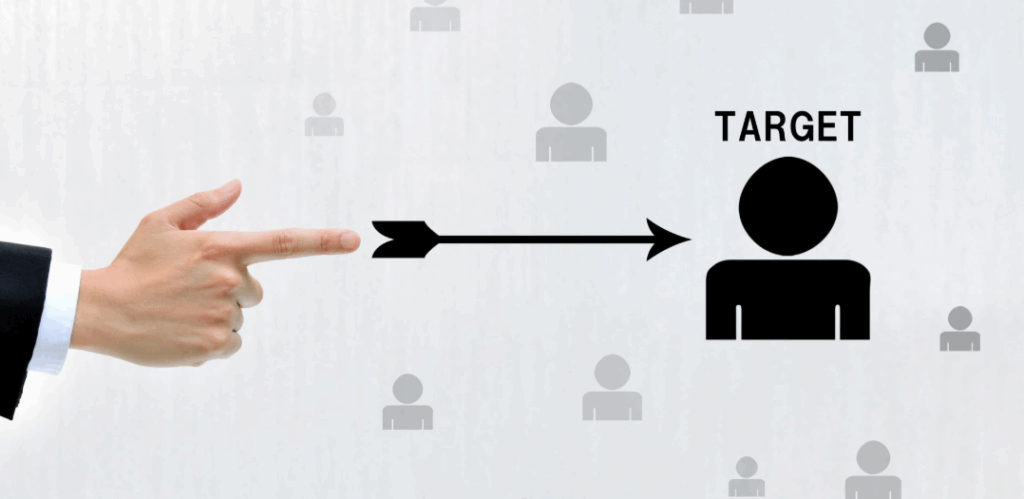
行政書士業務は非常に幅広く、「何でもできる」が最大の魅力でもあります。ですが、それをそのままホームページに反映させてしまうと逆効果です。なぜなら、人は「自分に合った専門家かどうか」が分からない限り、安心して問い合わせができないからです。
たとえば、「建設業許可が得意な行政書士」に相談したい人が、トップページに「相続」「離婚協議書」「内容証明」「風俗営業」「在留資格」…と業務が並んでいるのを見たらどう感じるでしょうか?
「この人、いろいろやってるけど建設業許可は本当に専門なの?」と感じて、他のサイトに行ってしまうかもしれません。
「何でもできます」では、だれからも選ばれません。「○○市の建設業許可に強い行政書士です」と明確に打ち出すことで、「それなら相談してみようかな」と思ってもらえる確率は大きく上がります。
特定の業務×地域で「検索にも強くなる」
さらに、ターゲットを絞ることはSEO対策(検索で上位表示されやすくする工夫)にも直結します。
「建設業許可 ◯◯市」
「離婚協議書 ○○区」
「在留資格更新 ○○県」など、検索ユーザーはピンポイントなワードで調べる傾向があります。
ここにピタッとハマるように、自分の強みと対象地域を絞り込んでサイト設計をすることで、見込み客とのマッチ率が一気に高まります。
いきなりすべての業務に対応する必要はありません。
むしろ最初は、自分が取りたい案件・得意な手続きに絞って作るのが成功の近道です。
その業務で実績や集客のベースを作ってから、少しずつ別業務へと拡張していくことも十分可能です。
【サービスメニューは明確に】料金・手続きの流れを見せる

ホームページを訪れる人の多くは「この人に依頼すると、何をしてくれて、いくらかかるのか」を知りたくて見ています。
ここが分かりにくいと、どんなに魅力的な文章でも不安になって離脱されてしまいます。
最低限、以下の3点はしっかり載せましょう!
価格や流れが見えるだけで、「イメージができる=行動しやすくなる」のが人間心理です。特に「行政書士に依頼するのは初めて」という人を想定し、「初めての方向けのページ」を別で用意するのも効果的です。
実績・対応地域をしっかり見せる

行政書士を探している人が次に気にするのは、「この先生、本当にうちの地域・この業務に慣れてるのかな?」ということです。
行政書士は、依頼者からすると「どんな人なのか見えづらい」職業のひとつです。そのため、ホームページ上で“信頼材料”をどれだけ伝えられるかが集客の分かれ道になります。
特に意識したいのが以下の2つです
どちらも、訪問者にとって非常に大きな安心材料となります。
実績は“数字・件数・業務名”で具体的に記載することをオススメします。たとえば、以下のように数字を交えて実績を記載すると、説得力が一気に高まります
- 建設業許可:新規・更新あわせて累計250件以上
- 宅建業免許:毎月3〜4件ペースで申請サポート中
- 相続関連業務:年間50件以上対応(遺言・遺産分割協議書作成など)
「何件対応したか」だけでなく、「どういう相談が多いか」「どういう業種のクライアントが多いか」まで書けると、より自分ごととして捉えてもらいやすくなります。
実績紹介コンテンツの工夫例:
- 実績一覧(カテゴリ別に整理)
- 業務事例(簡単なストーリー仕立て)
- お客様の声(可能であれば実名 or イニシャル)
- よくある質問とそれへの回答(実務経験が伝わる)
📌「行政書士には守秘義務があるから事例が書けない」という声もありますが、
実際の氏名や詳細を伏せたうえで、「○○市の建設業者様よりご依頼」などと表現すればOKです。
“ケースの雰囲気”が伝わるだけでも、訪問者にとっては安心材料になります。
実績×地域が「この先生に頼もう」と思わせる最大の要因
どれだけ実務能力があっても、それがホームページで適切に伝わらなければ意味がありません。
逆にいえば、“実績の見せ方”と“地域の見せ方”を工夫するだけで、問い合わせ数が2倍以上に増えることも珍しくありません。
検索され、見られ、信頼され、選ばれるサイトへ。まずは「実績と地域」から、強化してみてください。
プロフィールは“想い”まで書く

士業の中でも、行政書士は「人柄で選ばれる職業」です。同じ許可が取れるなら、「感じのいい先生」「話しやすそうな先生」に依頼したいと思うのが自然です。ただ、プロフィール欄が「出身校と資格名」だけでは、その“人柄”がまったく伝わりません。
▼より信頼されるプロフィールの書き方
例えば―
「私は元々建設会社に勤めており、現場や申請の実務を経験してきました。その経験を活かし、建設業許可に強い行政書士として独立しました。」
こういった「背景のストーリー」があると、訪問者が“この人に頼みたい”と感じる確率が大きく上がります。
問い合わせ導線は“何度も”出す
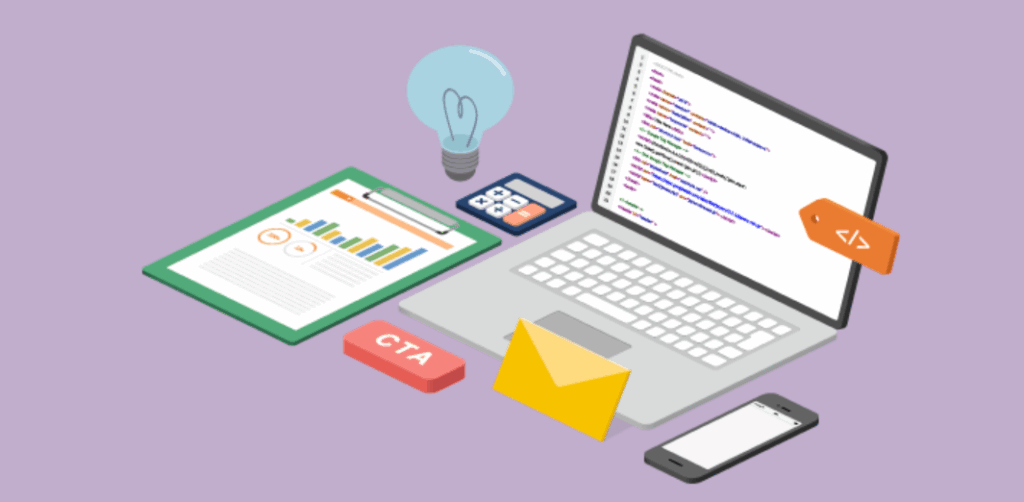
行政書士ホームページでよくある失敗が、「問い合わせフォームはあるのに、誰も使ってくれない…」というもの。
ですがこれは、フォームの内容や見た目以前に、「導線の設計」に原因があることが多いです。
結論から言えば、問い合わせを増やしたいなら、サイトのあらゆる場所に“問い合わせへの導線”を仕掛ける必要があります。
ユーザーは「ページを読んだ直後」が一番動きやすい
たとえば、訪問者があなたの「建設業許可ページ」を読んで「なるほど、分かりやすいな」「この人詳しそう」と思ったとしても、
そのページのどこにも相談ボタンがなければ、その気持ちは数秒で消えてしまうことがほとんどです。
人は行動のハードルが高いと、それだけで動かなくなってしまうからです。
効果的な問い合わせ導線の設計ポイント
各ページの最後に「ご相談はこちら」を入れる(必須)
記事や業務説明を読み終えた直後が、問い合わせのベストタイミングです。
その直後に「無料相談はこちら」「お電話はこちら」のようなリンクやボタンを配置しましょう。
ページ内の自然な流れの中にCTA(Call To Action)を差し込むことがポイント。
サイドバー・フッターにも常設する
ユーザーがページを読みながら「ちょっと聞いてみたいな」と思ったとき、スクロールを戻さずにすぐ問い合わせられるように、サイドバーやフッターに常設のリンクやボタンを置くのが効果的です。
フッターは全ページ共通なので、どのページからも問い合わせられる安心感を与える効果もあります。
スマホでは「固定の問い合わせボタン」が超重要
行政書士サイトの訪問者の7〜8割がスマホユーザーというデータもある中で、スマホでの導線設計は最重要です。
スマホでは、画面下に「常に見えている問い合わせボタン(フッターメニューや固定バナー)」を設置すると、どのタイミングでも即アクションできる設計になります。
▼スマホ画面下に固定表示されるボタンの例
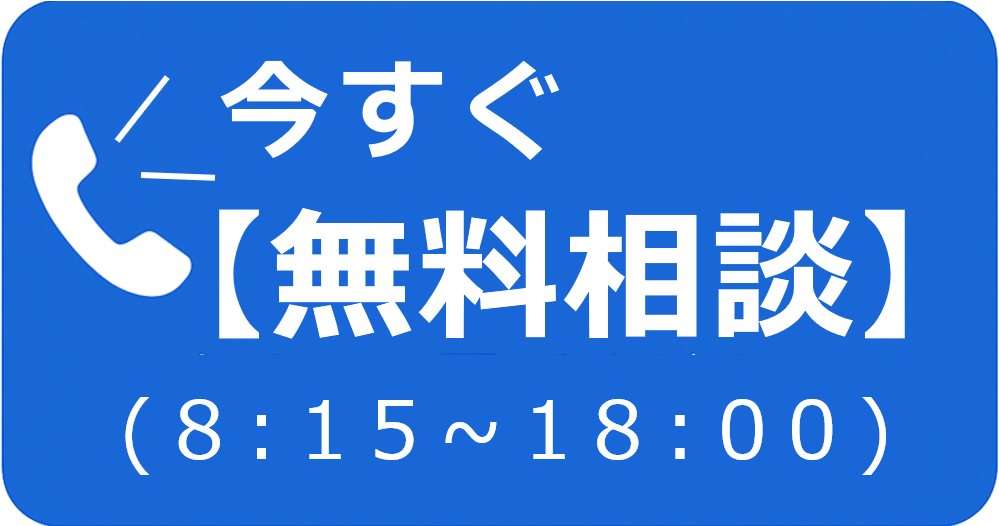


④ CTAボタンの文言にもひと工夫
「お問い合わせ」ではやや抽象的で踏み出しづらい人も多いため、「無料相談する」「まずは相談してみる」「簡単1分フォーム」など、“気軽さ”や“ベネフィット”が伝わる文言にすると反応率が上がります。
行動を促すには、“クリックする理由”を与えるのがコツです。
導線は「繰り返す」ことで効果が出る
「1ページに1回だけ」よりも、「3回同じボタンを見せる」ほうが、圧倒的に行動率は上がります。
これは「単純接触効果」と呼ばれる心理的現象で、人は何度も目にしたものに対して信頼感や安心感を持つようになるからです。
つまり、「見すぎてうざいかな?」ではなく、「もう一押し必要かも」と考えるのが正解です。
導線を複数設ける=ユーザーへの“おもてなし”
問い合わせ導線は、単なる「目立つボタン」ではありません。
それは、あなたの事務所に興味を持った人が「スムーズに最初の一歩を踏み出せる」ようにするための、おもてなしの設計です。
たった一言、「相談してみようかな」と思った瞬間に、1秒で連絡できる──。
それを実現するための“仕掛け”を、サイト全体にちりばめていきましょう!
コラム記事で“検索される入り口”を増やす

行政書士事務所のホームページに「集客力」を持たせるには、単なる業務説明ページだけでは足りません。
本当に重要なのは、検索ユーザーの「悩み」や「疑問」に応えるコラム記事です。
こうした記事が、Googleでの検索流入を生み出し、問い合わせにつながる“入り口”を増やしてくれる役割を果たします。
行政書士業務は“検索ニーズ”が明確だから記事化しやすい
行政書士の取り扱う業務は、ほとんどが「手続き」であり、ユーザー側にとっては「やり方が分からない」「失敗したくない」「自分でやるか迷ってる」といった強い不安や疑問が付きまといます。
つまり、それらをGoogleで検索して調べているユーザーが大量に存在するということ。
▼検索されやすい例
このような「悩み+キーワード」を記事にして、あなたのサイトに訪問してもらえれば、自然と信頼につながり、問い合わせの可能性が生まれます。
なぜ“業務説明ページ”だけでは足りないのか?
多くの行政書士のHPでは「サービス案内」「料金表」「プロフィール」だけで構成されており、
Google検索での“拾われる範囲”が非常に狭いのが実情です。
例えば「建設業許可 ○○市」で上位表示を狙うには、トップページやサービスページだけでは限界があります。
そこで必要なのが、関連する具体的な悩みやキーワードを拾ったコラム記事の量産なのです。
コラム記事のメリット(集客面)
- 検索流入が増える(= 無料で広告効果)
- ページごとに「○○キーワード+○○市」で上位表示が狙える
- 信頼・専門性が伝わる(記事を読む → 問い合わせにつながる)
- Googleに「このサイトは詳しい」と認識されて全体の評価が上がる
つまり、1記事=1つの集客窓口と考え、設計していくことが非常に重要です。
SEO効果を最大化するためのコツ
- 記事タイトルに「検索される言葉(キーワード)」を入れる
→例:「建設業許可に必要な5つの書類【東京都の場合】」 - 見出しに質問形式を使う(h2やh3に「〜とは?」「失敗例」など)
- 各記事に「関連記事」リンクや「無料相談はこちら」導線を入れる
- 地域名を必ず入れる(市区町村レベル)
まずは30記事から、“入り口”を広げていこう
目安としては、まず30記事を目標にするのがおすすめです。
1業務あたり3〜5記事ずつ書くと、自然と検索される“導線の網”が広がっていきます。
記事が10→30→50と増えるにつれ、サイト全体の評価も上がり、検索上位を取れるページが増えていきます。
スマホで見やすい=最重要
2割近くのユーザーがスマホから行政書士サイトにアクセスしています。つまり、「PCで見たら綺麗」かかつスマホでも見やすいことが重要なのです。
スマホ最適化チェックリストー
- フォントが小さすぎないか(16px以上推奨)
- ボタンは指で押しやすいサイズか
- メニューが分かりやすく整理されているか
- CTAや電話番号がすぐに目に入るか
- 画像やPDFがスマホで表示崩れしていないか
モバイルフレンドリーな設計ができていると、Googleからも「良質なサイト」と評価されやすくなり、検索順位にも好影響を与えます。
設計次第で「ホームページは24時間働く営業マン」になる

ただ見た目が整っているだけのサイトでは、行政書士業務の集客にはつながりません。
ターゲット設計・導線・情報設計・SEOのすべてが噛み合って、初めて問い合わせが生まれます。
実際に、設計を変えただけで「月の問い合わせが5倍以上になった」ケースも少なくありません。
行政書士として開業すると、最初にぶつかる壁の一つが「集客」や「営業の時間が取れない」という課題です。
日中は役所とのやり取りや書類作成、既存顧客との面談などで手一杯。
夜に一息ついたころには、もう営業のための動きなんて気力が残っていない…というのが現実です。
そんなときにこそ、“仕組みとして動いてくれる”ホームページの存在が非常に大きくなります。



